成熟した時代に自分自身は成熟しているか? 私が悩み多き人を好きな理由2025.01.10
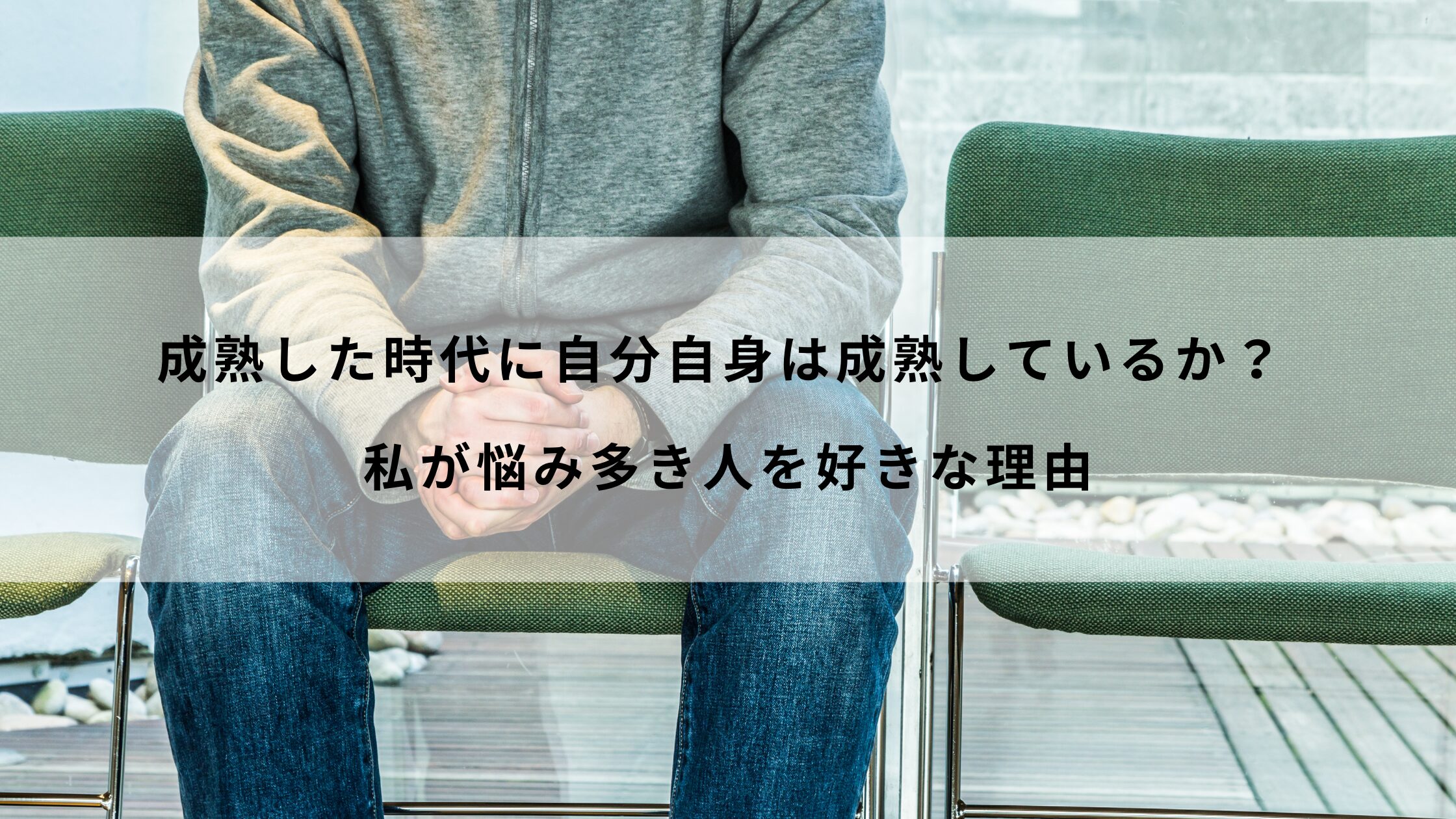
こんにちは。年末年始は、九州を満喫しました。
暦の休みが長かったこともあるのですが、かつてなく、満足度の高いお正月になりました。
暦の休みが長かったこともあるのですが、かつてなく、満足度の高いお正月になりました。

思うに、地方において自分軸で生きることが浸透してきたからではないか、と感じます。
東京で人の3倍働いてきて、その環境たまんない!!と思っていた私が、なぜ九州で満足のいく正月を送れる環境を作れているのか、それを少し振り返ってみます。
■なんとなく人が欲しがるものを欲していないか?
東京にいるときは、とにかく仕事も楽しく、生活も満足していました。同僚も優秀で、最先端のプロジェクトに関与できる、といった環境は、やはり世界都市ともいえる東京の醍醐味です。
また、稼ぎに合わせ、消費すること・体験できることも際限がなく、どこまでも求めていくことができます。
また、稼ぎに合わせ、消費すること・体験できることも際限がなく、どこまでも求めていくことができます。
地方で生まれた私は、この退屈で10年たっても変わらない街並みで、いつか家族を作り、毎月決まったお給料が振り込まれるであろう人生に辟易していました。
東京は、そんな私が、一念発起して飛び出してきた先として、とても魅力的な場所で、東京に住むことになったときから、「一生ここに住む!この価値観の下で生きたい!」と感じたことを覚えています。
東京は、そんな私が、一念発起して飛び出してきた先として、とても魅力的な場所で、東京に住むことになったときから、「一生ここに住む!この価値観の下で生きたい!」と感じたことを覚えています。
ただ、東京の生活にも慣れ、ある時、ふと立ち止まってみると、その巨大な規模、際限のない消費とその裏にある再現のない競争にちょっとした疑問を持つようになりました。ただ、あくまでちょっとした疑問です。
一度このレールに乗ってしまうと、なかなか「降りるのも怖い」という思いも同時に生まれていました。
自分で人生を切り開いていける感覚が好きで東京にいたはずが、いつの間にか、誰かの作った価値観、例えば年収であるとか、社歴であるとか、そういったものに支配されていっていたのだろう、と今になって思えば思います。
ある意味、硬直化していたのだと思います。
ある意味、硬直化していたのだと思います。
振り返ってみると、自分が欲しいものを得に来たはずなのに、いつのまにか、誰かが欲しいものを求めている自分になっていました。
もちろん、人生は何かを得る過程とも整理できる気がしていて、その感覚が間違っているわけではなく、資本主義を生きる私たちにとっては、「欲」は大きな原動力でもあると思います。
故に、僕が東京に感じていた違和感は、ある意味では違和感でもなんでもなく、それが正しいあり方である、とさえ思いますし、当時はその思いがとても強く、ちょっと変な感じするけど、これが正解だよなあ、と思っていました。
故に、僕が東京に感じていた違和感は、ある意味では違和感でもなんでもなく、それが正しいあり方である、とさえ思いますし、当時はその思いがとても強く、ちょっと変な感じするけど、これが正解だよなあ、と思っていました。

■有限を生きる覚悟ができたときに他人軸の上にはいられない
そのあと、私もサラリーマン人生を生きるに際して、偶然にも流されるように地元九州に戻ってきました。
最初は数年間居て、東京に戻っていくつもりでした。
東京の価値観が好きでしたし、多少の違和感を感じる程度で、キャリアも得て、自分なりに成功もしていましたので、居場所も東京にこそあるのだろう、と思っていたためです。
東京の価値観が好きでしたし、多少の違和感を感じる程度で、キャリアも得て、自分なりに成功もしていましたので、居場所も東京にこそあるのだろう、と思っていたためです。
当時の私の仕事は、事業再生でして、全国どこにでも仕事があるし、なにも九州で生きなくてもな・・と思っていました。
もともと九州は幼少期を過ごし、勝手知ったる場所なので、飽きるだろうし、短期間で動くことを前提としたいと思います。
もともと九州は幼少期を過ごし、勝手知ったる場所なので、飽きるだろうし、短期間で動くことを前提としたいと思います。
ところが、次の2点で、その考え方を改めるに至りました。
1点目は、人生の有限性を実感として得たことです。
東京から戻ってきたのが30代前半で、事業再生しているうちに、30半ばを迎えました。30半ば、というのは私にとっては難しい時期でした。
これまで成長一辺倒、上昇一辺倒で考えてくればよかったのですが、40になったとき、50になったときの未来が、なんとなく、遠い未来ではあるものの、透けて見える瞬間が、生活の中にチラつくようになりました。
極端に言えば、「老い」の始まりの一つなのかもしれませんが、人生が有限であり、今の時間は再度こない、という実感を得ました。
極端に言えば、「老い」の始まりの一つなのかもしれませんが、人生が有限であり、今の時間は再度こない、という実感を得ました。
2点目は、地方の認識を改める経験をしました。
九州に戻ってきて取り組んだ事業再生は、再生先に入り込んで、ともに企業価値向上と窮境を脱するために、あらゆる経営課題に取り組む、というものでした。
この仕事で、改めて、地場の方々とタッグを組んで、仕事をしていくこととなりました。
時々、東京からきて、計画だけ立てていくのではなくて、再生担当役員として数百名の職員がいる会社を立て直していくのですが、首までどっぷり、改めて地方に浸かる生活に挑むこととなりました。
時々、東京からきて、計画だけ立てていくのではなくて、再生担当役員として数百名の職員がいる会社を立て直していくのですが、首までどっぷり、改めて地方に浸かる生活に挑むこととなりました。
首まで使ってみると、当時若かった私が、退屈に感じていた価値観を大事にして、あえて選択してその環境にいる人の存在に気が付きました。
その価値観とは、たとえば人情、あたたかさ、個人至上主義でなく利他的な主義、地域とのつながり・連携、短期的でなく長期的・包含的な目線、そこに内包された歴史、伝承されてきた技術などです。
これらは一朝一夕にできるものでなく、そこを選んできた方々が長く培ってこそ、できるものです。
これらは一朝一夕にできるものでなく、そこを選んできた方々が長く培ってこそ、できるものです。
そうして、東京>地方ではなく、価値観に優劣はなく、それぞれが選択肢の一つであることに改めて気が付くことができました。

この2つの感覚からすると、有限な時間を過ごす中で、「何となく居心地がいいから、あるいは、今の自分に合っているから東京」と考えていくのは、ある意味思考停止だなと思い、残された有限の期間は、改めて自分軸で生きようと決めました。
もともとそうしたかったもので、どうしても見栄えがいいからとか、なんとなく安心だから、で、東京に残り続けていたのですが、地元を飛び出し、東京で鍛えてもらったおかげで、別にどんな環境であっても、自分は自分でやれる、という感覚も得ていたので、いったんフラットに考えてみよう、と考えることができるようになりました。
有限の人生を生きるときに、一番大事にしたいのは、自分の心地良さだよな、というシンプルな事実を、認めることができました。
今こうして文章で書くと、さらっとしていますが、当時はこの事実を受け入れるまで、相当期間、整理がつかないモヤモヤ期間を過ごしました。
見栄えがする、誰かが知っているファームで東京で働くほうがいいんじゃないか、リスクが低いんじゃないか、とか、東京に負けた男になるのか(なんか古いですね。)、など考えていましたが、事業再生をしていく過程で、いろいろな価値観に触れていき、「いや、そんな難しく考えず、自分の身体感覚を信じよう」と思えるようになったことを思い出します。
見栄えがする、誰かが知っているファームで東京で働くほうがいいんじゃないか、リスクが低いんじゃないか、とか、東京に負けた男になるのか(なんか古いですね。)、など考えていましたが、事業再生をしていく過程で、いろいろな価値観に触れていき、「いや、そんな難しく考えず、自分の身体感覚を信じよう」と思えるようになったことを思い出します。
最後は、自然と地方を軸に生きていこう、みたいなことを考えることができるようになりました。
■承継する会社は、そんな悩む人が集まる場所になるといいな
そんな中、当時創業60年の老舗IT企業である当社の承継を行う機会を得ました。
これまでのM&Aや事業再生(企業価値向上)の集大成としても面白そうですし、ITはある程度分かることもあり、二つ返事で引き受けました。
これまでのM&Aや事業再生(企業価値向上)の集大成としても面白そうですし、ITはある程度分かることもあり、二つ返事で引き受けました。
その承継に際して作る会社組織風土は、私のように、働くことや生きることを悩んだことがある人、あるいは、今後悩んでいく人が集まる場所にしていけたらいいな、と思いました。
なぜなら、仕事や生き方で悩む、というのは、ある意味本当にちゃんと生きていないとぶつからない壁です。一生懸命走ったことがある、あるいは走りたい、と思っているからこそ、悩むし、今のままでいいんだろうか、と考えるのだろう、と思います。
なので、当社においては、会社の目標とかKPIとか、そういうのはまあ考えてほしいけども、それよりも、自分自身がどうありたいかとか、何をなせたら幸せか、みたいなことでグズグズ悩もうぜ、と、話していて、それを方針の一つとしています。
KPIや業績を追うのは当たり前で、ある程度、それは所与の条件であるのですが、そこにこだわりすぎず、「あえて選んだ地方都市福岡で、仕事を通じて、どのような人生を送れたら幸せか」を大事にしてみています。
これは、いろいろ考えていくと、合理的で、答えのない、問いがそもそも正しいかすら不明確なこの時代において持つべき思考法を毎日セルフトレーニングしていることに他ならないためです。問いと解が整理されている場合のソリューションは、生成AIの回答で十分であることも多々あります。
そうなると、計算ドリルや解法を必死に覚える戦い方ではいずれ戦えなくなります。
なので、そういう問題を解くことにストップウォッチをもって挑む姿勢よりも、そもそも私たちが解くべき問いってなんでしたっけね、なんていう悠長なことを考えている組織って強いよな、そしてそんな心持の人が多い環境だったら、自分だったら働きたいな、と感じたため、SIやコンサルティングを生業としている会社の戦略・とるべき組織風土に合っているな、と感じました。
なので、そういう問題を解くことにストップウォッチをもって挑む姿勢よりも、そもそも私たちが解くべき問いってなんでしたっけね、なんていう悠長なことを考えている組織って強いよな、そしてそんな心持の人が多い環境だったら、自分だったら働きたいな、と感じたため、SIやコンサルティングを生業としている会社の戦略・とるべき組織風土に合っているな、と感じました。
■厳格な経営管理は行わないが、利潤を意識しなくなったら終わる
なので当社は、地方において、明確なKPIも組織にも個人にはおかず、輪郭や先行きにあえて余白を持たせていて、ふわっとした会社として運営されています。
ある意味、私が大好きであった東京の価値観からは離れた世界です。
ある意味、私が大好きであった東京の価値観からは離れた世界です。
ただ、急がば回れであり、不確実なことがいろいろ起きて、時には辛いことも大変なこともある中で、自分(人)や会社の成熟(必ずしも成長のみではなく)にはとてもいいと考えていて、当面はその方針で行きたいと思います。
かつて事業再生に従事していたときには、厳格なKPI管理や、数値マネジメントに傾倒していました。
数字こそが事実であり、短期的に生きていくことが長期を作る、余白は無駄であり、排除するべきものである、と本気で思っていましたし、今もその面がないわけではありません。
数字こそが事実であり、短期的に生きていくことが長期を作る、余白は無駄であり、排除するべきものである、と本気で思っていましたし、今もその面がないわけではありません。
かつての私は、今の私の一部であり、こういった感覚もまだまだ持ち合わせています。ただ、一番ではなくなりました。そういう経営管理技術も持っているが、別にそれはそれとして、一つの方法論に過ぎない、と考えるに至っています。
もっとも、この余白を大事にする意識だけ強すぎると、「稼ぐ」という概念を置き去りにしがちなので、月に1回は業績について振り返り、論理的に考えていくタイミングを持っています。
稼ぐことは大事で、「地方で横並びで、みんな仲良ければ貧しくてもいいよね!」みたいな牧歌的な生き方は、たぶん私自身には合わず、経済合理性を突き詰める数字をめぐる面白さと、本稿でつらつらと書いてきたような、迷いや余白を大事にするようなあやふやさを両方もっていくことこそが、地方に生きることであり、福岡に生きることじゃないかな、と思っています。ちゃんと稼ぐことは、会社が会社足るうえで大事です。それには、地方も都会もありません。
私は経営者として、集まってきた人たちの生活をよくしていくために、稼ぐことについては、やはり引き続き貪欲でないといけないな、と思います。
お客様をだまして、不当に儲けようということではなく、職員が提供してくれたサービスについては、適正な値付けをしていくこと、そして、その結果生じた利潤を、きちんと職員にも還元していく姿勢は、絶対に持つべきであると思います。
お客様をだまして、不当に儲けようということではなく、職員が提供してくれたサービスについては、適正な値付けをしていくこと、そして、その結果生じた利潤を、きちんと職員にも還元していく姿勢は、絶対に持つべきであると思います。

■迷える人はまだまだ増えるし、迷いの森からはでれそうにない
当社は迷える人がたくさんいますが、みんなで迷いの森を楽しく探索しています。遭難する人もたくさん出ますし、なんなら私自身も遭難しているのかもしれませんが、妙な納得感があります。
隠居して、森の木陰で休む、というのではなくて、リュックを背負い、登山靴を履き、森を歩き回って、熊から逃げる、そんな生活は割と楽しいなと思いますし、誰かの価値観で生きていない感覚があります。
積極的に迷う環境を意図的に作る、といった感じでしょうか。
積極的に迷う環境を意図的に作る、といった感じでしょうか。
なので、迷いに迷っているのですが、私たちには悲壮感もなく、迷っていることを楽しんでいます。
流石に取締役会は、経営の議論、戦略や組織の話をしますが、経営会議もシステマティックにやる面はあれど、あえて福岡でSIやコンサル・BPOといった知識産業をやっていく意義とか意味って何かね、みたいな禅問答から始まり、週末のおすすめお出かけスポットの話、森で焚火をした話(ガチに。)などを種々いろいろ話しつつ、仕事は仕事で、きっちっとまとめていく、みたいなことをやっています。
みんながそれぞれ迷い、時折、山小屋みたいな集合地点で邂逅したら、お互い近況を話すようなスタイルをとっているので、基本的に、各自が安全に迷えるよう、強い自立と自戒を求めているのも会社の特徴であり、誰かの何かにすがりたい、という価値観の元で生きたい場合には、非効率すぎて気持ちが悪いと思います。
ただ、当社のような考え方で運営している地方企業は、ある意味新しく、これからの衰退や、低成長の時代にはある生き方なのかなと思います。
私がお正月、最近自分軸で生きているよな……と感じることができたのは、普段からしっかり迷っていることにあるのではないかと思います。効率はとても悪いのですが、自分軸でしっかり生きられているからこそ、なんとなくの日々の満足感が高いのかな……などと思っています。
地方で”あえて”生きたい、自分の好きな生活がある方は、一緒に迷いの森の中で迷いましょう。迷うからこそ、新しい発見があるかもしれないし、迷うことこそ、もしかしたら人生そのものかもしれません。

少しでも「お!」と思われた方、気軽にアプライもしくはご連絡お待ちしております。
よろしければ、帰省や九州にお越しのついでにお話ししましょう。東京にもよくいますし、オンラインでもお話しできます。
よろしければ、帰省や九州にお越しのついでにお話ししましょう。東京にもよくいますし、オンラインでもお話しできます。

CONTACTお問い合わせ
戦略策定支援 / DXコンサルティング支援
/ SIサービス / BPOサービス、
採用のことなど、
お気軽にお問い合わせください。